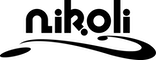20世紀クロスワード 解説裏話
解説裏話 その1、解説裏話 その3、解説裏話 その4、解説裏話 その5
アムンゼンの苦悩
前回につづいて、書ききれなかったことを紹介します。
ポツダム宣言の解説がないのがおかしいと思われた方もあるかと思いますが、短くすると誤解が生じそうなので、全文カットしたのです。原子爆弾も日本国憲法も東京裁判も重要ですから。
タテ427 ポツダムセンゲン
1945年7月26日、トルーマン・スターリン・チャーチルの三巨頭会談の結果出されたポツダム宣言は、日本の降伏をうながすものであった。ひらたく言えば「もう勝ち目はないのだから、降参しろ」ということであり、そこには「そうすればおまえたちの命だけは助けてやる」とう意味がこめられていた。これに対し、鈴木寛太郎は「黙殺」し、戦争を継続することを表明する。戦争終結をにらんで生まれた鈴木内閣であったが、少しでもよい条件の終戦を狙っていた。また、敗戦が左翼的暴動を引き起こすことを恐れ、面子の立つ形を求めていたのである。しかし、原爆投下とソ連参戦の結果、宣言受諾へ向かうことになった。御前会議は受諾の条件をめぐって紛糾するが、「国体の護持」つまり天皇制国家体制の維持だけを条件に受諾することになった。そこで、8月9日(長崎原爆の日)、「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す」と打電した。これについてのアメリカ国務長官バーンズによる回答が、8月12日入電する。それは「天皇の権限は連合国総司令部の制限の下に置かれる(これは表現をやわらげた外務省の意図的な誤訳で「従属する」と訳すべきもの)」としたうえで「最終的な日本の政治形態は、日本国民の自由に表明する意思により決定されるべきものとす」というものであった。天皇制を廃止するとも、存続を認めるとも明記されていなかった。しかし連合国の側からいえば「日本国民が認めれば天皇制存続を認める」ということであり、連合国内の対日強硬派に配慮しつつ日本の宣言受諾を引き出そうというギリギリのメッセージだったのである。バーンズらアメリカ国務省は、このときすでに天皇を日本統治に利用することを考えていたようである。昭和天皇は、バーンズ回答でかまわないという意向をすぐに東郷外相に伝えているが、それはこうした連合国側の意向を鋭く察知していたからだと思われる。こうして、日本の降伏がきまり、8月15日の玉音放送で国民はそれを知ることになる。しかし、その決断の過程には、国民の窮状への思いはなく、むしろ国民は暴動を起こす恐れのある存在と考えられていたのである。
また、日本の降伏を「無条件」ではないとする見解もあるが、ここでの「無条件」というのは「全く条件無しに」ということではなく、「日本からは条件をつけること無く」つまり「連合国の言うなりの条件で」という意味と解すべきである。「降伏」とは前述のように「言うことは聞くから、命だけは助けてくれ」ということであり、「命を助ける」「これ以上力を振るわない」という条件は、本来含んでいるものであり、それがあるからといって「無条件」でないという論は誤っていると思います。
また、前回述べたコスタリカ(タテ492)についての解説では、いわゆる「コスタリカ方式」についてのコメントもいれたかったのですが、行数の関係で断念したのです。
なお、小選挙区と比例区で同じ政党の二人の候補者が交互に出るのをコスタリカ方式と呼んでいますが、コスタリカの実態とは違ったよくない用語です。コスタリカは完全な小選挙区制ですが、政治家と選挙区の癒着を防ぐために、同じ選挙区での連続当選(というより、現職議員がその選挙区で立候補すること)が認められていないのです。そのため、2つの選挙区から1回おきに立候補する者がいるのです。地盤を継続するための日本のやり方とは、正反対なのです。「コスタリカ方式はよくない」なとど評するのは、失礼な言動というべきでしょう。
また、ひらやま氏が座談会でふれられているように、アムンゼン(ヨコ102)の記述も不十分でした。ひらやま氏から資料として送られてきたメールをそのままご紹介したいと思います。
1906年北西航路を発見したアムンゼンの次の目標は北極点到達だった。同じノルウェーの先輩極地探検家であるナンセンが北極海で使った探検船フラム号を借りることにし、北極行きの準備を進めていたアムンゼンの耳に入ったのが、アメリカのピアリー隊が北極点初到達に成功したと言うニュースである(ピアリー隊北極点到達は1909年4月)。北極点初到達の目標を失ったことに大きな打撃を受けたアムンゼンだが、ひそかに目標を南極に変更する決意をする。しかし、計画を変更したことをアムンゼンは周囲に対して秘密にしていた。理由の一つは、北極行きとして資金を集めた手前、勝手に目標を変更することに対する支援者たちとの関係を慮っため、もう一つはイギリスが国を挙げて大規模な南極探検計画を進行中であり、計画の公表が無用な国内外の議論を引き起こすことを恐れたためである。こうしてあくまで北極行き(科学的調査と理由づけた)と称して、1910年8月、アムンゼン一行を乗せたフラム号はオスロ(当時はクリスチャニア)を出港した。フラム号がモロッコの西にあるマディラ島に寄港したとき、隊員とその他の乗組員に初めて南極行きが打ち明けられる。隊員たちは情熱を込めてこの案を支持したという。同時にアムンゼンは既に洋上を南極に向けて進んでいるイギリスのスコット隊に向けて「われ南極に向かわんとす」との電報を打つ。こうして強敵アムンゼンの出現はスコットの知るところとなり、人類史上最も過酷な舞台において、国家の威信を背負った2組の長きに渡るレースは対決の火蓋を切った。
アムンゼンの本心は北極点到達にあったことを示す証拠に、1912年12月に南極点到達を成し遂げた際を振り返ったアムンゼンの手記がある。「ゴールについた。旅は終わった。”我が生涯の目標が達成された”--といえば効果的表現になろうが、私にはそうは言えない。それではあからさま過ぎて、むしろ作り話めくだろう。私は正直に告白するが、このときの私ほど、自分がゴールを望んだ地点とは正反対の場所に身を置いた者がかつてあっただろうか。北極周辺、いや北極点そのものこそが、私の少年時代からの憧れだった。それがいま南極点にいるのだ。これほど逆さまなことが世に想像できようか(以下略)」