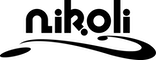しかし、書店を回っているときに「大手の版元が来年パズル雑誌を創刊するみたいだよ」と聞いて初めて将来のことをなんとなく想像する頭になっていった。
樹村も彼女なりに書店や読者からの電話の応対、バックナンバーの置き場、会計のやりくりなどで今のやり方に限界を感じとっていたようだ。
私は編集、制作については会社でやっている仕事の延長線上のことなのでそこに問題はなかったが、営業と配本に限界があり、運転免許を取った。
一気に新刊の配本期間を短縮したがそれでも10日はかかり、書店から「もう出ているみたいだけど何でウチには来ないの」という電話がかかってくるようになっていた。
この先どうするかなあ。
口火を切ったのは樹村だった。
「最近しつこい電話が来るのよ。読者だと思うんだけど、ここに来たいって。あなたの方も在庫をおいておくところ、もうないでしょ」
「うん」
樹村は私より二つ年上である。清水は私より二つ年下である。
「で、そろそろ事務所があってもいいと思うんだけど」
「そうだなあ、その方がいいかもしれんなあ」
「で、あなたこれから先どのようにしたいと思っているの?」
「まるで考えていなかったわ。ちょっと考えてくる」
夏が終わろうとしていた。
一晩寝て起きてニコリ1本にすることに決めた。女房は「あら」と言った。