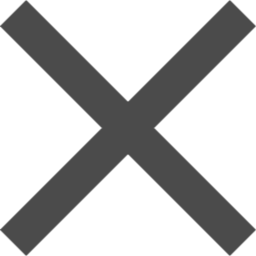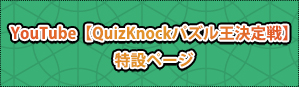1988年のニコリを振り返る
1988年に発売されたニコリ
20号 1月1日発行
21号 4月1日発行
22号 7月1日発行
23号 10月1日発行
1988年のニコリを振り返る
季刊化2年目となった1988年。発行日も狂うことなく順調に号を重ねていきました。誌面の内容に大きな変化はありませんでしたが、その後のニコリ、およびパズル界に大きな影響を与える「オモロパズルのできるまで」がスタートしたのがこの年です。
20号の特集のテーマは、数字の「20」。この後の特集は、動詞や数字などいろんなテーマでお送りするようになります。
「パズル病棟日誌」では「ロープパズル」を掲載。これは読者に難解なパズルを出題してその最善解を競うという一種のコンテストで、この時期は何度かこの種のパズルが出題されました。
21号では、「オモロパズルのできるまで」が始まりました。第1回は、A.P.A氏が考案した、線を引くパズルを元に、ルールと盤面のスタイルをいろいろいじるコーナーでした。
その他のパズルでは「雀パイブロック」が大サイズで登場。麻雀好きにウケ、その後も細々ながら長く掲載されました。
19号で募集した「清少納言知恵の板コンテスト」を改め「テングラムコンテスト」がスタート。その後、ナイングラム、エイトグラム、シックスグラムとピースの数が減ったり増えたりし、「清少納言知恵の板」と同じ「セブンピース」に戻るのは、26号です。ちなみにこの号から本誌の表紙には、このコンテストの優秀作が飾られるようになります(21号ではスタッフ作の例題)。
22号では、前号の雀パイブロックに負けじと、ナンバーリンクが大きいサイズ(15×15マス)で登場します。
前号から始まった「オモロパズルのできるまで」では、轟由紀氏の「三角ヌリ」(のちのトライアングル)が登場。以降、読者が新しいパズルを考案して発表する場として発展していきます。
新コンテスト「十七文字さんこんにちは」がスタートしました。最初は「いろは」の3部門があり、「い」は有名句を並べ替えて新句を作る部門(現在と同じ)。「ろ」は元句を伏せて使用文字だけあかして並べ替える部門。元句を当てる楽しみもアリ。「は」は回文句などを募る自由部門でした。
23号では、「日曜日に町を作る」が完結編を迎えました。
この時期はいろんなパズルが大サイズで掲載されていますが、この号では懸賞パズルの「解読ボード」が2ページで登場。ルールは単純でも、大きいというだけで難問になってしまうことがわかったのでした。
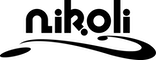
 パズルが遊べる
パズルが遊べる